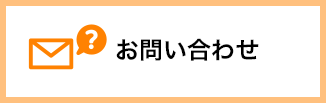仕事と生活をあえて区別しない「公私融合」を取り入れる企業が増えている理由

画像:New Africa/AdobeStock(※)
仕事とプライベートをあえて明確に線引きせず、どちらも充実させていく「公私融合」が、メディアなどで紹介されはじめています。たとえば、子連れの出勤が認められたり、社内で趣味的なサークル活動が行われたりするなど、さまざまな取り組みが行う企業があるようです。今回は、識者や企業の声を聞きながら、この公私融合について考えてみました。
■柔軟な働き方に対応し、人材確保のために導入
まず、企業の働き方に詳しいPRアカデミーの栗田朋一氏(代表取締役)に、「公私融合」が注目される社会的背景や、社員を家族に見立てていた昭和の日本企業との違いなどについて伺いました。
――最近、公私融合という動きがありますが、取り入れる企業は今後増えていくでしょうか。
栗田 今後、そうした企業は増えていくと思います。理由は、そうしなければ人材確保が難しくなっていくためです「社員一人ひとりのニーズや業務内容に応じた柔軟な働き方を支援する」という企業の声もあります。また、「そもそも公私を分けた働き方をしていない」という企業も出てきています。
――どんな実例があるでしょうか。
栗田 2014年設立のあるITマーケティング会社では、職場に子どもを連れて来ることが許されています。社員が集まる月次の定例会に、お子さん連れで参加している役員やメンバーが数名いるそうです。同社では毎月2回、ストレッチの先生を呼んでメンバーも就業時間中にレッスンを受けることができ、社長のご家族も一緒に受けられることもあるそうです。
また、2017年設立のベンチャー企業では、出社義務や副業許可などのルールが定められておらず、自分のミッションを遂行していればそれ以外の時間は自由に使うことができるといいます。
■公私融合のメリットとデメリット

PRアカデミー 代表取締役 栗田朋一氏
――公私融合すると、企業と従業員にはどんなメリットがあるのでしょう。
栗田 家庭と会社が完全に切り離されている働き方では、獲得できなかった人材が入ってくることにより、会社の戦力が上がることが考えられます。たとえば育児や介護、趣味、ボランティア活動などに時間を割きたいために退職する、あるいは会社にいられなくなるというケースを防ぐ効果も考えられます。
従業員にとっては、今の仕事を続けるために子(育児)や親(介護)の世話をあきらめるのか、または生活の中での癒しや安らぎ、楽しみ(趣味)を捨てるのかといった、究極の選択をしなくても済み、仕事と生活のどちらも選べるという世界が広がり、やりたいことを諦めなくてもよくなるのではないでしょうか。
職場としても、子どもやペットを連れて来られたら、フレンドリーでアットホームな雰囲気になり、パワハラやセクハラなどは減るのではないかということも期待できます。子どもの前でそのような振る舞いをする人はいないと思いますので。
また、言い出しにくいことも言え、頼みづらいことも頼めるような助け合いの組織ができるはずです。ギスギスした関係が払拭されるので、ストレスが軽減され、従業員も健康的な生活が送れるようになると思います。
――逆にデメリットも考えられる?
栗田 「プライベートまで社員と仲良くしたくない」「プライベートはしっかり確保したい」という人はこの風潮に馴染めず、会社を離れていくこともあり得えます。また、仲の良さが甘えに転じ、人任せな仕事をする人が出て来る可能性もあります。それによって他の従業員のモチベーションが下がり、ひいては顧客の満足度低下につながる恐れもあるかもしれません。この制度(公私融合)を享受できる人と、できない人が出てくる可能性もあり、不平等感が生まれることもあるでしょう。
■「体験型」旅行で社員の親睦を深める
――かつての日本企業には、社員運動会や慰安旅行、事業所ぐるみの地域行事参加など、公私融合的なイベントが普通にありました。現代的な公私融合はどこが違うのでしょうか。
栗田 以下のような点が昔と違うところだと思います。
(1)部署横断型でプロジェクトを組み企画・運営する
昔は総務部など特定の部署が担当して、他の社員は決められたことに従うしかなかったところがあります。今は複数の部署から人を出し、そのメンバーで運動会の種目や進行、社員旅行の行き先や行程、部屋割りなどを決めていきます。一から企画し、あらゆる場面を想定し当日に備える過程が、仕事にも生かせると考える経営者は多く、何より、普段一緒に仕事をしない他部署のメンバーと一つのことをやり遂げることで一体感が生まれ、部署間の意思疎通がスムーズになります。
(2)ただ行くだけでなく、行って何をするかの「体験型」
社員旅行は、ただどこかへ行って楽しんだり観光したり交流を深めたりするのではなく、農家の人たちと田植え、収穫などを手伝ったり、被災地へ赴いて復旧作業を手伝ったり、仕事に関係した何かを身につけるための研修旅行だったりします。日本一のおもてなしを学ぶために加賀屋に行く会社もあり、社長が「神社参拝」に関する本を出したCOBOLという会社は、社長の想いをみんなで体感するため、神社巡りの社員旅行をしました。
(3)会社が全額負担
給与の一部を積み立てして旅費に充てるのではなく、全額会社が負担することが多くなっています。積み立ての場合は旅行に参加しなかった社員にお金で払う必要が出てきますが、そもそも全額会社負担だから不参加者に払い戻す必要はありません。これによって参加率が非常に高くなります。会社にとっては、社員のために使いたいと思う経営者も多いのではないでしょうか。
■継続的な「部活動」ではなく、1回きりの活動「社内サークル」
次に、占い事業やアーティストファンビジネスを中心としたBtoC事業を展開する株式会社CAMを訪ねました。同社ではこれまでの部活動を改め、社内サークル制度を導入し、公私融合的な取り組みをしています。膽畑(いはた)匡志さん(取締役人事責任者)、大仲正泰さん(人事Div.)、田口佳澄さん(コーポレート・リレーション室)のお三方にお話を伺いました。

株式会社CAMの皆さん。左から膽畑(いはた)匡志さん、大仲正泰さん、田口佳澄さん
――社内サークル制度を導入された背景についてお伺いします。
田口 当社にはもともと「部活動」というものがあり、社員がもっと気軽に参加できるよう、それを「サークル活動」としてアップデートしました。オフィスが渋谷と中目黒の二つに分かれているという背景もあり、サークル活動では社員間の親睦を深めたり、コミュニケーションを活性化させたりすることを目的にしました。
また、会社のビジョンである「Be a Fanatic.」(熱狂する)を体現し、ユーザーに熱狂を届けるためにも、社員どうしでの熱狂をつくりだし、私たち自身が熱狂するきっかけを作るというのが大きなコンセプトとしてありました。
――従来の「部活動」との違いは?
大仲 カメラ、サッカー、野球、ゴルフなどの「部活動」がありましたが、活動実態はほとんどなく、社員からは「部活は活動要件が細かいので改善をしてほしい」という声がありました。「サークル活動」は、1回きりの活動で終了するというところが部活とは違います。また同じことをやりたかったら、再度申請すればできます。人気があれば、継続的に活動しているサークルもあります。
■誰でも手を挙げられる手軽な運用
――会社にとっては運用の手軽さがあるということですね。
膽畑 拠点が2つに分かれているという課題があったので、コミュニケーションが活発になるように、もっと気軽にシンプルな運用にしたいと考えていました。そのようなタイミングで、「サークルみたいな形でやっていきたい」と田口から提案がありました。とにかく提案も実施も手軽に、誰でも参加できるようにルールを最低限に絞り、スタートしました。 サークル活動制度は無期限ではなく、制度自体がいつか終わる可能性もあります。現在はとりあえず1年やってみよう、という段階です。こういった制度は皆でつくっていくことが大事だと考えており、自分たちが使いやすいように変化させていくのが理想です。
――これまでにどんな活動をしていますか。
田口 2019年の4月にスタートしてもうすぐ1年になります。活動実績としては23回、参加人数は延べ256人です。当社の従業員が304人ですから、社員は一人一回くらいサークルに参加していることになります。1回の活動のハードルを低くしていて、身体の危険を伴うような活動以外は基本的に認められます。これまでに脱出ゲームやボードゲーム、フットサル、ボルダリングなどがありました。PIXAR展を観に行くサークルには、デザイナーがこぞって参加したこともあります。その時々で、行きたい人が集まれるのが最大のポイントです。
■拠点間の交流を活性化し、会社が一枚岩になれる仕掛け
――身体の危険を伴う活動以外に、NGなことはありますか?
大仲 嗜好品をたしなむのはNGにしています。たとえば水たばこ、日本酒サークルなどです。単に嗜好品を味わうのが目的であれば、個人でやればいいので、会社として補助を出す必要はないとの判断です。ただしパン作りの活動は実績としてあります。これはパンを作るということがメインになっているので承認されたケースです。
――申請のフローについて教えてください。
田口 まずは活動を企画する人(責任者)がGoogleフォームで申請します。フォームはビジネスチャットアプリのSlack上にあり、いつ何をやるのかを申請してもらいます。これは認めていい活動なのかどうか悩む場合は、人事内で相談しています。
膽畑 申請に対して人事が上から判断することはなく、実態としては、ほとんど現場の田口と大仲の二人で判断しています。かなり迷ったときに、私に意見を求められるくらいです。私が判断している感じでもなく、運用をかたくるしくしないことが重要です。その代わり、半年に一回、振り返りをやります。この制度のバージョンアップや改善点などを話し合っています。
――田口さんは、どんな思いからサークル制度を提案されたのでしょう。
田口 社長の飯塚勇太は当社代表としては3代目で、就任したのが18年12月でした。会社として変化のタイミングでもあったので、社内の交流を深めたいという思いがありました。拠点間の交流をさらに活性化し、会社が一枚岩になれる仕掛けが必要だと考え、サークル制度を提案しました。
■参加を促すには、地道な声がけも必要
――活動報告はどのように行われ、サークル制度が社内の活性化につながっているような事例はありますか?
大仲 サークルの終了後に、活動レポートを提出するのをマストにしています。活動内容と集合写真は必須要件になります。写真は、これを見た従業員が「自分も参加しよう」と興味を持ってもらうために、なるべく現場の雰囲気を表した写真の撮影をお願いしています。活動の成果としては、新卒が社内に溶け込みやすくなるという効果を期待しています。例えば、執行役員と新卒が一緒にいるようなサークルもあります。終業後に会社の会議室で開いた「人狼ゲーム」には、社長の飯塚が参加していました。サークル活動は休日が7-8割、2-3割が終業後というのが、これまでの活動状況です。
――公私の融合が進むと、仕事とプライベートが曖昧になる懸念はありませんか。
膽畑 これは私の推測ですが、「仕事は仕事で割り切りたい」という人たちは、そもそも当社には少ないかもしれません。インターネット関連の企業で、とくにエンタメ系事業を扱っている我々のような会社は、そういった傾向があるように思います。もちろん従業員のプライベートの時間も大事にしたいという考えはもっています。
大仲 当社には本社のある渋谷から二駅までは家賃補助が出る、というルールがあり、利用者は若い社員が多いです。会社のメンバーが同じ町に住んでいたり、土日もよく飲みにいく仲間がいたりする、という現状もあります。そうしたなかで、体を動かすサークルが自然と立ち上がったりしています。社員の平均年齢が31歳で、年が比較的近いので、社員どうしの仲はいいと感じています。
――立ち上げ時にはどんな苦労がありましたか?
田口 導入当初、マニュアルを作りましたが、個別に質問がよく来ました。「みんなに見られるのは恥ずかしい」「どのラインの活動までが承認されるのか」といった相談です。そこは細かくケアしていました。当初は、サークルが承認されるか分からないので事前に相談をされるということが頻繁にありました。大変だったというより、数をこなしたという実感はあります。
運用面では、社内限定のオウンドメディアを立ち上げ、Slackのチャンネルだけでなく、全員が見られるところに活動のレポートを貼るようにしました。誰がどういう活動をしているのかをいつでも見られる環境に置いています。サークルの申請をしてくれた人のランキングなどもつくって社内で発表したりもしています。
――もともと社員同士のコミュニケーションが活発な社風があったのですね。
膽畑 活発な方だと思います。とはいえ油断すると、事業ドメインもいくつかあるため、部門間を超えたコミュニケーションが減りがちです。オフィスが分かれることによって物理的な距離がうまれるようなことは、やはり放っておくと起きてくると思います。
当社には新卒育成を目的とした独自の制度「Cheers(チアーズ)」というものがあります。所属する部署以外の先輩社員である"Cheer(チア)"となり新卒社員全員につき、定期的に様々なコミュニケーションを通して、新卒のみなさんを応援する取り組みです。応援者をつけることで、会社全体で応援する雰囲気をつくっています。
たとえ良い仕組みを作っても、それだけは回らないものです。そこには誰かの熱量が必要で、結局はみんなに声がけして参加者を募るといった、地道な取り組みも必要になってきます。サークル制度でいえば、はじめに田口が率先してやってくれたことが、初動の良さにつながっていると思います。

株式会社CAMの社内サークル活動.の様子(画像提供: 株式会社CAM)(※)
今回、公私融合について識者や企業に取材する中で、「仕事と生活のどちらをとるのか」という二者択一的な働き方は、時代にそぐわなくなっているのを感じます。高度成長期の日本企業のように、社員が社内行事に半ば強制的に参加させられることも少なくなりました。 現代的な公私融合は、社員の自発性や体験型の取り組みがカギを握るのではないでしょうか。
取材協力
株式会社PRアカデミー[外部リンク]
株式会社CAM[外部リンク]
編集・文・撮影:アスクル「みんなの仕事場」運営事務局 (※印の画像を除く)
取材日:2020年2月18日
2016年11月17日のリニューアル前の旧コンテンツは
こちらからご確認ください。