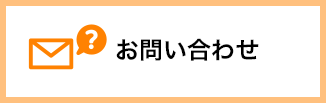世界のビジネスエリートとの仕事に不可欠な美術史の教養とは? 〜西洋美術史家 木村泰司氏インタビュー

西洋美術史家 木村泰司氏
欧米諸国のビジネスパーソン、特にエグゼクティブたちの多くは、教養豊かで、ビジネスディナーの席や社交の場ではそのような幅広い知識を持っていることを前提に会話が繰り広げられます。逆に商談はできても、ビジネスディナーで教養を感じさせるような会話ができないと、ビジネスパートナーとしての親交を深めていくことは難しいとされます。
『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)の著者、西洋美術史家木村泰司氏にビジネスシーンで欧米のビジネスマンとコミュニケーションを図る際の美術史の知識を中心とするリベラルアーツ(一般教養)の重要性についてお伺いしました。
■ビジネスパーソン向けの美術史の本が生まれたきっかけ
――木村さんは美術史家でありながら、ビジネスマン向けに本を書いたり、企業向けセミナーの講師などをされたりしていらっしゃいますね。
ダイヤモンド社から"読む美術史"の本を提案いただいて2017年に出版したのが『世界のビジネスエリートが身につける教養 西洋美術史』という本ですね。"読む美術史"をテーマに書きたいと思っていたので引き受けたのですが、自分にとって第2のデビュー作と言えるほど注目を浴びました。
――"読む美術史"とはどういう意味でしょうか?
私は、いたるところで、美術は見るものではなく読むものだと伝えてきました。宗教画から発展した西洋絵画は、とくに19世紀以前は歴史画を頂点としたジャンルのヒエラルキーがあったため、絵画は宗教的な教え、神話のエピソード、政治的なメッセージなどを伝えるために描かれてきました。それらの作品には、各時代、各地域、社会の事情が「反映」されていますので、それを読み解くということです。
――その"読む美術史"がビジネスパーソンのニーズにマッチしたのですね。
まず、企業に講師を派遣する会社から契約を依頼されました。それまでは論語をテーマにしたり、そしてやはり実務的な内容の講座が多かったらしいですが、西洋美術史の講義ができる人が欲しいということでした。そのタイミングで本が発売されたので、さらに企業向けセミナーが増えたのです。
――どういった企業から依頼があり、どういった方が参加されるのでしょう。
東京の企業が中心で、金融、航空会社、流通、メーカーまで様々です。セミナーは銀行主催で法人メンバーを招待するもの、幹部候補生のみが参加するもの、社員の中で希望者が参加する手上げ式のものなどがありますね。大阪では毎日21世紀フォーラムに招かれ、企業トップの方々を相手に話をしました。
以前はファッションブランドを持つアパレル企業や外資系投資銀行が顧客向けに主催する食事会や講演会に招かれることが多かったんです。ブランドの顧客向けイベントの参加者は女性がほとんどでした。それが次第に男性の多いビジネスパーソン向けのものに変わって来た感じです。
――書名の"ビジネスエリート"が、ビジネスパーソンの興味を引いたのでしょうね。
書店でビジネス書のコーナーにおかれたこともヒットした要因だと思います。前からビジネスパーソン向けの講演依頼もあったのですが、本が出てから一気に増えましたね。ダイヤモンド社から出た第1弾はギリシャから近代の美術史を解説したものですが、その第2弾『世界のビジネスエリートが身につける教養 名画の読み方』では、宗教画、歴史画というようにジャンルに分けて紹介しました。そして、かつての電子書籍にしたものを生かす形で、今年1月に『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』を出版しました。
――ルーヴル美術館を取り上げられた理由は?
ルーヴル美術館は、イタリア、フランスなど国別にギャラリーが分かれています。美術館によっては作品を寄贈したコレクター別に展示しているようなところもありますから。この本ではルーヴルの展示に沿って、それぞれの国別に美術史を紹介しています。全体で西洋美術史をとらえるより、国別に辿った方が理解しやすいと思ったからです。
また、ルーヴルはもともとフランス王家のコレクションを中心に展示をしてあるため作品のレベルも高いし、日本人にとっては馴染み深い美術館ですよね。ツアーでパリに行く日本人は多いし、大抵はルーヴル美術館を訪れるのではないでしょうか。私がルーヴルで案内しているように書いたつもりですので、例えば電子書籍版をガイドブックのように使っていただければ嬉しいです。
――ビジネスパーソン向けに美術史の本を書こうと思われたきっかけは?
あるグローバルな企業の方から「日本人は欧米人が相手だと2時間のビジネスディナーがもたない」と言われたことがありました。その企業のトップの方はアメリカ留学経験があり、語学も達者で、海外にもよく出かけられ、出張先で美術館を訪れたりされるそうです。来日した欧米のエグゼクティブが西洋美術の企画展を見たいと美術館に行かれた際、社員にお付き合いさせたところ話について行けず会話が続かなくて困ったというのです。
■美術史はエリートや上流階級に不可欠な教養だった

――語学が堪能でビジネスの話はできても、文化教養的な話題では会話ができないと。
欧米企業の管理職は日本のように下から上がってくるのではなく、最初からエグゼクティブとして会社に入ります。いわゆるエリート教育を受けていて、理数系でも経済専攻でもリベラルアーツ(一般教養)を学んだ人たちで。イギリス王室のウィリアム王子とキャサリン妃が、大学で美術史を専攻していた時に知り合ったというエピソードがあるように、美術史は欧米ではエリートに不可欠な教養とされていますから。
――エリートや上流階級のたしなみなのですね。
チャールズ皇太子も建築に造詣が深いことで知られていますが、18世紀当時のイギリス紳士にとって必須の教養は建築、美術、ラテン文学でした。もともと明日のパンに困る人が学ぶものではない学問だったわけです。
ただ、啓蒙主義が台頭し、王家が所有していた美術品を民衆にも公開すべきという声があがり、ヨーロッパの美術館の時代が始まります。フランスでは、革命の後、王室の美術品が国有化され、さらにナポレオンが戦利品として諸外国から持ち帰った美術品をナポレオン美術館の名前で公開しました。これがルーヴル美術館の始まりです。
バイエルン王国のルートヴィヒ1世も美術愛好家ですが、美術品は国民のもの、と捉えて19世紀に現ドイツのミュンヘンにあるアルテ・ピナコテーク美術館を開館しました。
――その時代に美術がポピュラーなものになったのですね。それまでは一般庶民は美術品を目にすることもできなかった。
はい、啓蒙思想によって、国民の美意識も高めていかなければならないという考えが生まれ、美術館はいわゆる教育機関として生まれたわけです。王侯貴族であれば、美術品に囲まれて育ち、それを理解する教養も身につけています。そのような環境にはない一般庶民が美術の読み方を学ぶ、つまり、絵が描かれた背景に何があったのかを学ぶために美術史が発展し、体系化されたわけです。絵画にタイトルが付けられるようになったのもその頃からですね。
――今では誰でも気軽に美術館で作品を鑑賞できる時代になりました。
とくにヨーロッパでは子どもへの美術史教育が浸透しています。イタリアで美術館に行ったとき、修学旅行の小学生たちが絵画作品やその歴史の説明を受けていました。パリに住んでいた知人も小学校の課外授業で市内の美術館に子どもたちが行く機会があると言っていました。図工が中心の日本の美術教育とは異なるのです。
昨年10月にアルテ・ピナコテーク美術館に行ったときに、20歳くらいの学生2人がある古典絵画の前で作品について延々と語り合っていました。自分もかつて美術の勉強のためにイギリスに留学していた時は友人と美術館に出かけて、作品について意見を交しあった思い出がありますが、日本ではあまり見られない光景です。美術史教育が浸透していないからでしょうね。
■美術史を通してヨーロッパの歴史、政治、宗教、価値観、社会が見える

――先ほどの美術館で会話が続かなかった社員も、美術史の知識があれば違ったということですね。
西洋美術史を知ることは、ヨーロッパの歴史とキリスト教が西洋文明にもたらしたものを知ることで、それぞれの国の歴史、政治、宗教、価値観、社会が見えて来ます。それがグローバル社会でのコミュニケーションに役立つのです。たとえば、2019年のノートルダム寺院の火災に、なぜフランス人があれほどショックを受けたのかも理解できるでしょう。
――"世界のビジネスエリート"のシリーズを読んで、実際にビジネスシーンで役立ったという読者の声はありましたか?
このシリーズを読んで美術史に興味が湧き、私の講座に通い始めた人は少なくありません。以前はカルチャーセンターの講座は主婦が主でしたが、最近ではビジネスパーソンがずいぶん増えています。海外赴任経験があり、現役をリタイアされた方もいらっしゃいますが、駐在中に美術館をいろいろ巡ったけれど、そのときは美術史の知識がなくて絵を見ても理解できなかったのが残念だとおっしゃっています。
ビジネスシーンで役立てばいいですが、それ以外にも、プライベートで海外に出かけて美術館へ行くときや、日本で西洋美術の企画展に行くときにも、美術史の知識があるのとないのでは違いますから。
――ビジネス書のコーナーに置かれたことで、新たな美術ファン層を開拓されたのですね。
私は常日頃から17世紀に活躍したフランス人画家ニコラ・プッサンを知らずしてフランスの美を語るなかれと話し、フランス人に「好きな画家は?」と聞かれたら、プッサンと答えなさいと半分冗談で生徒に言っています。
ある日、講座に参加した女性がパリで5つ星ホテルに泊まったところ、コンシェルジュは初めはけんもほろろな態度だったそうですが、ルーヴル美術館でプッサンの画集を買って、それを抱えてそのコンシェルジュの前を通ったら、それ以降、彼女に対する態度がよくなったそうです。
■リベラルアーツを身につけるには、まずは興味を持つこと。

――知は力なりですね。美術史をはじめ、ビジネスパーソンがリベラルアーツを身につける効果的な方法はありますか?
まずは興味を持つこと。興味を持って学べば身に付きます。本を読むという行為が大切ですね。いろいろな講座に通うのもいいでしょう。今の時代はインターネットで本に載っていない知識を補充することもできますよね。美術史に関しても、今はインターネットでルーヴル美術館の作品が見られます。もちろん実際に訪れることができればそれが一番いいのですが。
――『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』の反響はいかがですか?
残念ながら新型コロナウィルス感染症の影響で、今、カルチャーセンターは休講で、生徒たちに感想を聞くことができていません。書店で行われるはずだった出版記念イベントも中止になってしまいました。
ただ、内容が流行に左右されたり、時代遅れになったりするものではありませんから。
また、この本はカラーで画像も多く読みやすくしてあります。ビジネスパーソンにかぎらず、西洋美術に興味のある方にお勧めできる本です。新型コロナウィルスの問題が終息して、また皆さんが海外旅行に出かけられるようになれば、パリでルーヴル美術館に行く予定の方にはぜひ読んでいただきたいですね。
■お気に入りの記事はこれ!
――「アスクル みんなの仕事」でお気に入りの記事を教えてください。
日本点字図書館 長岡英司館長のインタビューです。
「ITを活用して視覚障がい者の就労機会を増やしたい ~日本点字図書館 長岡英司館長インタビュー」
じつは以前、拙書の点字化の打診をいただいたことがあり、とても感動しました。私は書籍が持つ力を信じていますので、それを広めるために、日本点字図書館の今後のより一層のご発展を願うばかりです。

西洋美術史家 木村泰司氏
欧米のエグゼクティブたちと会話ができるような美術史の教養を身につける、と聞くと身構えてしまいますが、木村さんのお言葉通り、興味を持つことのできるテーマの知識を身に付けて行くのは、仕事にもプライベートにも役立つ楽しい作業のように思えました。
プロフィール
木村泰司(きむら たいじ)
西洋美術史家。1966年生まれ。米国カリフォルニア大学バークレー校で美術史学士号を修めた後、ロンドンサザビーズの美術教養講座にて WORKS OF ART 修了。ロンドンでは、歴史的なアート、インテリア、食器等、本物に触れながら学ぶ。知識だけでなくエスプリを大切にした、全国各地での講演会、セミナー、イベントは新しい美術史界のエンターテイナーとして評判をよんでいる。
テレビやラジオなど各メディアで幅広く活躍している。
著書
『名画の言い分』(ちくま文庫)[外部リンク]
『名画は嘘をつく1~3』(大和書房)[外部リンク]
『世界のビジネスエリートが身につける教養 西洋美術史』(ダイヤモンド社)[外部リンク]
『世界のビジネスエリートが身につける教養 名画の読み方』(ダイヤモンド社)[外部リンク]
『人騒がせな名画たち』(マガジンハウス)[外部リンク]
『世界のビジネスエリートは知っている ルーヴルに学ぶ美術の教養』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)[外部リンク]
『教養としてのロンドン・ナショナル・ギャラリー』(宝島社新書)[外部リンク]
編集・文・画像:アスクル「みんなの仕事場」運営事務局
取材日:2020年3月11日
2016年11月17日のリニューアル前の旧コンテンツは
こちらからご確認ください。