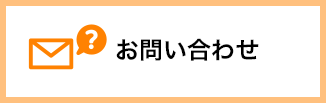【岸本章弘のワークプレイス新潮流インタビュー[5]】建築家小堀哲夫氏が実現した「目標の見えないワークプレイス改革に形を与える」共創プロセス <後編>

(左) 岸本章弘氏(ワークスケープラボ)、(右) 小堀哲夫氏 (小堀哲夫建築事務所)
(編集注) 本記事は、2020年2月27日に取材しました
求められる活動や意識をユーザーチームとすり合わせながらイメージを共有し、デザインの解像度を上げていく共創型のプロセスによってNICCA INNOVATION CENTER、梅光学院大学The Learning Station CROSSLIGHT を手がけられた小堀哲夫氏にお話を伺った。
前編はこちら 「【岸本章弘のワークプレイス新潮流インタビュー[5]】建築家小堀哲夫氏が実現した「目標の見えないワークプレイス改革に形を与える」共創プロセス <前編>」
≪日華化学株式会社イノベーションセンターと梅光学院大学新校舎の紹介≫
日華化学研究開発拠点「NICCA INNOVATION CENTER」

繊維用薬剤メーカー日華化学が2017年11月に竣工した研究開発拠点。延床面積7,495.73m²、執務用総席数200席。社内企画部門は同社イノベーション推進本部、設計担当は小堀哲夫氏。2018年度「JIA 日本建築大賞」(日本建築家協会主催)受賞。(写真:新井隆弘 ※)
日華化学株式会社イノベーションセンター[外部リンク]
梅光学院大学新校舎(北館)「The Learning Station CROSSLIGHT」

梅光学院大学開学50年記念事業の一環として建築を進め、2019年3月に竣工した新校舎。地上3階、延床面積3,947.79m²、椅子数は1階197脚、2階367脚、3階105脚(造作家具は含まず)。設計は小堀哲夫氏。「アジアデザイン賞_金賞/DFA Design for Asia Awards 2019, Gold Award」「日本タイポグラフィ年鑑2020 部門別ベストワーク賞」など受賞。(写真:Nacasa&Partners ※)
梅光学院大学新校舎[外部リンク]
■多様なキャラクターの共存と連携を支えるオフィスへ
岸本 かつてのオフィスは組織そのものを配置しており、ピラミッド状の組織図をパタンと倒すとオフィスのレイアウトになりました。でも、今のABWやセミラティス構造のように縦横につながる組織のための空間になると、ツリー構造ではなくなり、アクティビティを配置したオフィスになる。「組織の配置から機能の配置へ」の転換ですが、設計するためには従来のような組織のデータではなく、アクティビティを観察したりリサーチしたりしなければならなくなりました。さらに言えば、リサーチできるのは現状であって、それを変えていきたいのに、どう変えていくのかは当人たちにも見えていない。でも、考える場や道具を提供して、具体的に一緒に作っていくと、当人たちも思っていた以上のポテンシャルを発見できる。それを追うために前向きに取り組んでいけることは、きわめて重要なことですね。
小堀 そうなんですよね。部長がいて課長がいて平社員がいて、というビジネスシーンは、合理的に早く生産してお金が儲かっていた時代のものです。しかし、今の日本で新しいキャラクターや商品が必要になったときに、そういうヒエラルキーからは今まで想像もしなかったものは生まれないことが分かってきた。
そこにあるのは、スピードの差なんですよ。部長まで届くのにすごく時間がかかってしまう。だからネットワーク型の機能別の場を瞬時につなげられる仕組みを持った場がイメージできるわけです。それを上下左右360°すべて立体的につながれば情報量が最も多くなり、それが知識の立体化にもなる。要は脳を立体化したような空間です。人々が出会い、瞬時にものごとを考えることができ、新しい創造性のつながりができる空間。
都市もそうですよね。今の渋谷や六本木、新宿などは、様々なものが表出化していて、すぐアクセスできる新しい都市で、そこには場としてのキャラクターがある。日本全体が、そういう場のイメージが分散化してネットワーク化されている。僕は都市構造をそのまま空間化するのも非常に有効な手立てではないかと思う。街を歩いているように働こうみたいな感覚を持ち得ると、みんなが働き方を脱構築できる気がします。
その先どうなるのかは僕にも分からないけど、今、テレワークで意外と仕事できるとわかってきているので、自分たちが場に縛られていたことに気づきはじめるでしょう。企業にとっては厄介なことに、社員から利益を絡め取ることができなくなる。資本主義の空間というのはピラミッド構造で成り立つねずみ講のようなものだから、みんながそれぞれでつながり始めると崩壊するんじゃないかな。場のない形でみんなが勝手に商売を始められるわけだから。
岸本 制度的にも、副業や兼業を認めはじめていますしね。
小堀 そうすると誰でも資本主義の頂点に立てることになる。働き方というのは、そういうところまで連鎖していくよね。皆、働く意味を考えはじめる時代に突入したと思っています。そうするとオフィスはキャラクターの時代にいくんじゃないか。さっき、機能別と言いましたが、キャラクターですよ。ここに行けば自分はこうなれるというキャラクターが乱立するようなオフィス空間に、自分も身を置きたいと思える場を作っていかなければならない。
岸本 コスプレみたいなものですね。この部屋にいる私はこういう私、というように、場によって意識的に演じることで身についていくこともあるから。「組織から機能へ」というのは第一歩でしかなく、その次のステップへ行こうとしているのかもしれない。
小堀 組織から機能へ、機能からキャラクターへ、となり、そのキャラクターをどう空間化するかということが僕らの次の興味になっています。
今、CICというプロジェクトをやっているのですが、ボロノイというグリッドを組んでいて、全部が違う部屋なんです。設計変更で壁の位置をずらすとき、グリッドプランだとすべてに影響するからけっこう大変なのですが、ボロノイという生命体のようにセルがくっついているプランは、壁を動かしても一部しか動かす必要がない。その周辺しか動かす必要がないんです。
参考:
「世界につながるイノベーション発進基地 ケンブリッジ•イノベーション•センター」[外部リンク]
「世界最大級のイノベーションコミュニティCICが、 アジア初のセンターを2020年7月東京虎ノ門にオープン -- CIC」[外部リンク]
今までの何かが起こると全体が崩壊してしまう組織は、じつはリスキーなのではないか。たとえば一部の人が変わっても、その部分だけキュッと補完できるネットワーク化された組織と空間が大事かなと思います。
梅光学院大学の「365の椅子」もそういう意味だと思います。一律の家具を置くと、そのうちの1個が廃番になると全部ダメになる。予算が足りないと全部一律にコストダウンしなければならなくなる。でも365種類の椅子を置けば、もともとバラバラなんだから、1個廃番でなくなって別の品番の椅子を入れても誰も気づかない。そういう組織形態、運営形態が今後成立していく気がしているんですよね。梅光学院大学ではそういう議論をずっとしていました。

(写真:新井隆弘 ※)

同じ椅子がひとつもない(写真:新井隆弘 ※)
とくに学校はヒエラルキー型の組織だから、どうやってフラットにするかを考えた。そこでやったのが、個室だった研究室を一つの共同研究室に集めてフリーアドレス化すること。教員はどうしても研究室にこもってしまうから、学生たちが行き交う1階に全員集め、教員の蔵書もオープンシェルフに入れて、誰もが見られるようにしたんです。

(写真:小堀哲夫建築設計事務所 ※)

(写真:小堀哲夫建築設計事務所 ※)

教員の蔵書をオープンシェルフに入れ、教職員をフリーアドレス化(写真:小堀哲夫建築設計事務所 ※)
岸本 各人専用の鍵のかかるボックスがついています。あれをパタンと開くとちょうどデスクになって仕事ができる。
小堀 教員が1階で学生と話し込んだり、学生が集まってきたり、そういうシーンは今までの大学ではなかった。これまで隣の教員が何を研究しているのかも知らなかったんです。そこで商業施設のようにインフォメーションセンターを作って、教員と職員と学生が3人座るようにした。学生はアルバイトでお金もらえる。教職員同士が話すようになる。
セミラティス構造と言っていますが、セル同士が立体的に交差して、廊下がなく、全部教室なんです。教室の中をつっきって行く。授業を聞く権利も、参加する権利も与えてみる。こういう空間構成が教育にどのように影響するかというと、「俺はこういう授業をしてみよう」という話が生まれるんですね。
1階のカフェレストランは地域にも開放されていて、大学生協の運営でワインも飲めるようにしました。

(写真:Nacasa&Partners ※)

カフェレストランでの演劇授業の様子。(写真:小堀哲夫建築設計事務所 ※)
小堀 こういう階段も教室なんです。空間と活動の連携がすごくうまくいった例ですね。
これは学校側が学生を使って作った動画ですが、交差していくイメージを表現しています。階段と教室、持ち運びのボックスを作って。短焦点プロジェクターで壁全体がホワイトボードとスクリーン。床にも書ける。全員タブレットPCを持って、ペーパーレスが可能で、教材はクラウドから自分でとって、すぐ授業が始められる。

(写真:梅光学院大学 ※)

大階段でのレクチャー(写真:小堀哲夫建築設計事務所 ※)

(写真:梅光学院大学 ※)
梅光学院コンセプトムービー(youtube)[外部リンク]

(写真:梅光学院大学 ※)

(写真:梅光学院大学 ※)
小堀 面白いのは、家具と建築の境がないことで、僕らはプラットフォームとしての場だけを作って、造作は全部家具側の工事でしたが、互いの領域を行ったり来たりすることをワークショップでやっていた。岸本さんを含めてインターオフィスの家具デザイナーもお互いの領分を少し広げながら混じっていく関係性が、セミラティス構造なんです。「あなたはこの分野だけ」という合理的な分担では何の創造性も発揮できないんですよ。
岸本 効率的なプロセスじゃなくて、効果的なプロセス。あの建物は学校だけど、社員何百人かの会社ならそのまま本社としても使えると思いました。大小様々な空間があり、遠くで起こっていることも何となく見えたり聞こえたり、気配が感じられたり、しかもどこでも動き回れることを前提としていて、あらゆる部分に情報を映せるようになっている。ネットワークもつながっているし、生活の場としてのカフェやライブラリー、一人で篭れるスペースもあれば、少人数で打ち合わせできるし、大人数でも会議ができる。講義型の研修もできる。ひと通り揃っています。
今、オフィスが要らないと言われる理由のひとつは、どこでもオフィスとして使えるからです。アクティビティを切り分ければカフェでも自宅でもできる。でも集まって何かをする場所は多くない。どこでも仕事できると言っていますが、テレワークでは、まだリアルタイムに集まるワークショップはできない。生身の身体があるかぎり、物理環境としての快適性も必要だし、会議と会議の合間のソロワークのために、いちいち自宅に帰るわけにもいかないでしょう。だからそれなりに多様なアクティビティに対応できる集まる場所が必要なんですね。
デスクワーク中心の従来組織を配置した空間ではなく、チームワーク、コラボレーション、インタラクションを中心とした空間の中に、合間にはちゃんとソロワークもできる場所があり、生活空間としてのサービスもあるという方向に持っていかないと、楽しくないと思います。
■場の選択肢を使い分ける自由と不自由

小堀哲夫氏
小堀 難しいのは、今、働く場が増えていますが、そうなると働く側に強靭な目的が必要になる可能性がある。じつはみんな型にはまりたがっているんだよね。たとえばコンビニでどのお茶を買うか、選択肢がありすぎて悩むことないですか。だけど、最高の1杯っていうのが求められるなら、僕らはそれを作りたいし、それを選ぶ側もしっかりと目的を持たなきゃいけない。
今、たくさんのコワーキングスペースができていますが、どこでもあるとなったときに、逆に高度化というかプロトタイプ化してくださいという人たちが表出する予感があります。新しい場の在り方を提示しないとバブル崩壊みたいになるんじゃないかな。どうですか、食べ放題だと食べる気がなくなることってないですか。
岸本 最近のコワーキングスペースはニーズがあるから増えているというより、スペースがあるから新しいニーズを探し求めている面があると思います。企業が積極的にコワーキングスペースを活用する理由は、シンプルにいえば効率の問題ですね。スペースのコストが下がればいいという話だし、テナントとして補償金を払って一定期間リースするより、柔軟に使いこなしができる。必要なら増やせるし、必要なければ減らせる。それはそれでファシリティの管理からいうと効率的です。
人事管理まで含めて企業側のマネジメントニーズにうまく対応できているのは、以前に取材したワークスタイリングでした。
過去記事:「【岸本章弘のワークプレイス新潮流インタビュー[2]】"適業適所"に働き、イノベーションを引き寄せる場の選択肢としてのシェアオフィス「ワークスタイリング」」
これからは会社員として働くモードと、個人として働くモードの併存が可能になります。副業が認められていても、会社のオフィスで副業の仕事をするのは気が引けるからコワーキングに行く。あるいは、自分の中でメリハリをつけてモードを切り替えるために、自宅に帰らずコワーキングで仕事をする。空間によって脳も切り替わるし、周りにいる人に合わせて空間を使い分けることができればいいですが、使う側にもそういうリテラシーが必要ですね。
実際に使い分けようと思っても、移動には時間がかかるから、リアルな移動と身体があるかぎりは、じつは何でもかんでも自由になるわけではないんです。そこをうまく組み合わせたときに、生き残っていくところが決まっていくのだろうと思いますね。
小堀 自分の働き方を俯瞰的に見直すと、つねに働いているんですよね。これだけ働くと、自分は誰のために働いているのかと思うことがある。自由なようで自由ではない。
岸本 つねに型を破り続けるのは苦しいから、型を使い分けることも必要ですね。個人の拠点を1ヵ所持ったり、チームの拠点を作ったりして、ここにいるときはこれをしようとか。
小堀 その通りですね。脱構築したうえで、もう1回再構築していく。働き方から自由になって、新しい自分なりの働き方を見つけるゾーンにいかないと苦しい気がするんです。
岸本 マンネリ化しないように、つねに俯瞰してチェックすることが必要だと思います。そのためには経験の繰り返しが要る。会社員は、入社するとOJTからスタートするから、一回それを壊してみる訓練が必要だと思う。
そのためのステップとしてワークショップを考えると、みんなでやったり、プロの助けを借りてやったり、リアルなプロジェクトの中でやってみたりするのはけっこう重要だと思うんですね。
従来のようなやり方では新しい空間を作れないかもしれないと考えたときに、「一緒に作る」という作り方があると思うんです。空間デザイナーが支援することでユーザー自身にとっての新しい働き方、新しい空間ができる。
小堀 僕のプロジェクトに共通しているのは、参加した全員が、自分たちで作ったと思っているということです。圧倒的なプロとしてのデザインは挿入していますが、与えられたものではないということがすごく重要で、オフィス作りの最大のテーマはそこだと思います。これからは働く場を自分たちで作れる時代になっていくし、脱構築と構築を繰り返すような場のつくり方になると思います。つねに変化しつづけることを目指してはいても、フレキシブルな多目的空間型とは違う。僕らはいつも絶妙なバランスで空間を構成していますから、日華化学や梅光学院大学をはじめ、様々な研修センターや研究所もつくっていますが、じつは毎回トライ&エラーなんですよね。そういうとクライアントに怒られるかもしれないけど(笑)。
岸本 トライ&ラーンでいいんじゃないですか。やってみて学んで、また次やってみて学んで。
小堀 トライ&ラーンですね、まさしく。ここで発見したことを次のプロジェクトに活かしていく。ワークショップも含めて身体的なところから組み立て、大きさ、高さ、暗さ、匂い、風とかも含めたひとつの環境をパッケージとして提案していきます。デザイン的なシンキング方法でオブジェクトを出しながらワークショップして、みんながアーキテクトになっていく感じが比較的うまくいっている気がします。
岸本 毎回トライがあるわけですね。従来の設計プロセスに比べると、時間もかかるし、新しいことも必要だし、手助けしてくれる専門家も必要だし、効率的ではありませんよね。加えなければなりません。それでも効果があるからやっていると。
■個の環境はキャラクター化する

岸本 今感じていること、一番直近にラーンしたことで次にトライしてみたいこと、この辺が課題かなと思っていることはありますか。
小堀 逆説的に言うと、タコツボをどうつくればいいのかと思っているんです。今までタコツボをオープンにと言っていましたが、人間とはアンビバレントな存在ですから、オープンにすると今度は個室が欲しくなる。本当の個室の在り方とは何か。先ほど話したCICは個室の連続です。いろいろな企業が入るのですが、場はもう固定されていて人間が動く、つまり2人になりたかったら2人部屋に行くという考え方です。すると場がどうしても多様化せざるを得ないから、100通りの部屋があるという世界観で設計しているんです。
だから今、僕の中では、オープンという空間のジレンマに悩んでいます。梅光学院大学ではセミオープン、セミクローズという言葉を使ったのですが、オープンの対極としてのクローズな空間の在り方をどう共存させればいいのかが非常に難しい。ヤフーのイノベーショングループが働いている「ロッジ」に取材に行ったのですが、オープンなやぐらの中で、とても働けないと言って逃げちゃったのね。真面目なイノベーターは自分で動ける能力を持っているから、会いたいときに会えて、会いたくないときは会いたくないという両方が必要です。それがどういう空間の在り方になるかということに興味があります。
参考:Yahoo! JAPANのオフィス内にあるオープンコラボレーションスペース「LODGE」[外部リンク]
もうひとつは、これまでの日本企業は「創業者精神を学ぼう」という大家族主義の絆の下で信頼を構築しようとしてきました。創業者精神を結束力のバインドとする「家族」というコードに当てはめて組織運営してきた。ところが、グローバル世界では、多種多様な人間をバインドする「キャラクター」という世界が必要になる。日本の大家族主義が悪いとは言いませんが、家族ではない他人をオフィスの中に受け入れ、自分も他人の中に入り込める空間構造に、今非常に興味があります。
「ロッジ」はそれを実験的にやったし、梅光学院大学も今やろうとしていて、登録すれば高校生も自由に使えるようにしました。第三者が入ってくるわけです。「ロッジ」も高校生やお母さんやおじさんが利用してもよくて、ヤフーはそのデータを蓄積してマーケティングに利用することで、ある意味ひとつの構造の中に絡め取ろうとしているのですが、もっとフリーな状態とはどういう状態なのか、ひとつの空間として成立しうるのか、ということに興味があります。
CICは面白いと思いますよ。ティムさんというアメリカの代表が言っていたのは、人間は最終的に物理的な距離が近ければ近いほどいいということです。だからとにかく同じ場所に集める。日本代表の梅澤さんという人も、日本にイノベーションが起きないのは、歴史的なことと構造的なものだと言っています。イノベーションはマネー・タレント・アイデアの3つが同時に揃わないと生まれないが、日本ではそれが同じ場所にないというんです。金を出す投資家と、それを実現化するデザイナーと、タレント、アイデアマン。ティムさんがCICを作ったのは、ハーバードとMITの近くにあるカフェでその3つが揃ったからなんですって。
キャラクターの濃いギラギラした3人をどうつなぐか。そのための活動プログラムがベンチャーカフェというカフェ運営なんですよね。あの企業の考え方はすごく面白い。 そういう尖ったキャラクターの場が都市に生まれると、シーンによって自分が動きはじめる時代になってくる気がします。そういうオープンな交流の場とそこを行ったり来たりする空間の在り方が今興味のあることです。
岸本 ノンテリトリアルと言っておきながら自分の拠点が欲しいですよね、やっぱり。
より効率的な方向に動こうとするのが生物としての本能で、余計なことは考えない、余計なエネルギーは使わない。それをあえて壊してばかりだと疲れてしょうがない。いったん壊したから当面はこのままでいいよねとフィックスしたほうが、次を壊すためのエネルギーを蓄えるためにもいい。拠点を持つこと、変えていくことの全体を俯瞰してチェックしながら、必要に応じてトライし修正することが必要なのかな。でも、それを組織レベルで行うのは容易ではなく、一人ひとりのペースも考えるとなかなか厄介ですね。
小堀 僕なりに実践しているのは、不安定な場所を作るということです。イライラしたり、むしゃくしゃしたりした瞬間に生み出されるアイデアにはすごく価値があると気づいたんです。あえてそういう不安定な場所に一歩踏み出せるかということが、クリエイティビティにおいて非常に大事。でも、そういうふうにできない人もいる。結局、最終的に安定側に行こうとするトリガーになるのは環境なんですよね。違和感や不安感のある場と居心地のいい場を行ったり来たりすることは結構大事かもしれないと思う。自分を型にはめようとする力からどうやって解放されるか。若いときは簡単にできたと思うけど、今は自発的にやらないとダメ。
岸本 面白法人カヤックに「旅する支社」という制度がありましたね。期間を決めて2~3カ月間、イタリアに住居兼オフィスを借りて、実際そこで仕事をしていた。場合によっては日本時間に合わせて早朝仕事をしなければならないから、日中はイタリアの日常を体験できたり。そこに一時的に暮らしてみる感覚ですね。
小堀 面白いですね。子どもってワクワクとドキドキが両存していますよね。脳科学者が言っていましたが、ワクワクとドキドキを感じる前頭葉は同じ部位だそうです。ワクワクは楽しい、ドキドキは不安。たとえば塀の上を歩いたり、ジャングルジムの上に立ったり、そういう子ども特有の感覚は、たぶん何か創造的なプロセスなんですよ。それが固定化されると、ドキドキしたくないと思いはじめるんです。ドキドキとワクワクは表裏一体なのに、ドキドキをリスクと捉えはじめると、それを回避するためにお金を投資してワクワクだけを得ようとするんです。それは何の解決にもなっていない。ワクワクしたかったらドキドキするところに行け、と思うのですが。
■キャズムを越えるための「他者」の存在

岸本章弘氏
小堀 これ間に合うかなと思う瞬間、すごいスピードで作らなきゃいけない瞬間にこそ、圧倒的なクリエーションとワクワクが出てくることにわれわれは気づいているから、グワーッと追い込んでいくんですよ。
岸本 従来のやり方では何が足りないのかいまいちわからなかったクライアントは、このインタビュー記事を読んでもらって、デザイナーにもっと要求すればいいんじゃないですか。そうすると受けた側は追い込まれて、やらざるを得なくなる。
小堀 イノベーションキャズム理論も同じです。キャズムをジャンプできる人は、ジャンプ力があって、ドキドキにチャレンジできる人です。ほとんどの人はそれが無理なんです。たとえば親が死んだり恋人に振られたり、圧倒的な外的要因がないと、自分から飛び込んでいかない。どうしようもない外的要因でキャズムをジャンプできた瞬間、新しい自分がいる。じつはそれは建築に近いと僕は思っている。建築と空間の場ができあがってポンポン飛ぼうとしているのを見ると、空間とか環境と、ワークショップも含めたそのつくり方は本当に重要で、同じ金額を投資するならそこまでやったほうがいいと言いたいのね。ただ箱を作ってくれ、面積が足りないから何平米くれと依頼するのではなく。今そのチャンスであると捉えられることは非常に重要だと思います。
岸本 梅光学院大学と日華化学の場合は、上田先生のような新しいやり方や理論、手法を持ち込んでくれる人がいましたね。必ずしもいわゆる建築家サイドだけではなく、ユーザーサイドにももっとこんな人がいてくれたらということもあります。そういうプロセスをうまく効果的に、場合によっては意図を超えて壊していけるプレイヤー、キャラクターがいれば面白いんじゃないかと。もちろんユーザーの側でも、プロジェクトには絶対にキーマンがいるじゃないですか。梅光学院大学の場合、あの学院長でなかったらあそこまでいかなかったし。
小堀 こういう商売をしていていつも思うのは、設計者がクライアントを超えられないのは宿命なんですよ。クライアントが要らないと言ったら終わりですから。大体、クライアントはクライアントの世界観、過去の成功体験でしかものごとを考えられない。われわれデザインする側は、それを超えた未来の提案をしているので、それを想像できないんです。だからクライアント対デザイナーはだんだんギクシャクしていくわけですよね。
プロジェクトというのは、場づくりをすると、どうしても過去の成功体験に引きずられます。過去の経験やヒエラルキーがすごかったりするとなおさらです。最初のワークショップでは盛り上がっても、机についた瞬間にただの人になって、「そうはいってもさ......」と現実に引き戻される。それを回避するためには、われわれ側じゃなくてクライアント側をディレクションできる人材を常に用意してもらう必要がある。破壊的イノベーション的な感性を持っていて、超越的な発言をしてくれるアートディレクターがプロジェクトにいると、ものごとを気づかせてくれるんです。僕らは会社に入り込めないから、「そうはいっても現実はやっぱり違うから......」というときに、「そうじゃないぞ、やってみよう」と言ってくれる人が要りますよね。
岸本 「ワークショップは盛り上がったけど......」というのはきわめて現実的な問題ですね。
小堀 「いろいろ勉強になりました、ありがとうございます」ではなく、何回も口酸っぱくして、「やっぱりやってみようよ」と言っていく必要がある。こういうワークスペースのプロジェクトは非常に複雑に絡み合っているからね。
あるプロジェクトでは、儲かっている部署と収益構造の変化で儲からなくなる部署をつなげようとしているのですが、保守的なピラミッド構造の組織とけんかして大反対されています。やはり社内にそういう破壊的イノベーターを一人置いておく必要を感じますね。「本当にそれでいいのか」と言える人材を雇えるか、他社でもいいしコンサルタントでもいいのですが、ちゃんと金払ってそういう「変態」というか、彼らが想像できない「他者」をオフィス内に呼び込めるか。
岸本 内側からかき回してくれる人。
小堀 日華化学には吉田さんという役員でもありアートディレクション的な立場の人がいて、「本当にそれでいいのか」と僕らと掛け渡し、ワークショップにも参加し、勉強会もやりながら付き合ってくれた。そういう人が企業内にいるのはすごく強みだと思うんですよね。
岸本 様々なイノベーティブなオフィスでも、そういうキーパーソンがいて、その人がいなくなるとやがてうまく機能せずに廃れていくことがありました。その人が去るまでに、その遺伝子で風土を変えていけるかどうか、引きついでいく人を残していけるか。
小堀 ワークショップで成功したのは、みんながそんなキーパーソン候補になって巣立っていったことです。日華化学の場合は、その中から「イノベーション企画部」というのができ、参加者の女性2人が中心となって運営しています。今ではMO-SO活動など様々なことを企画している。もともと他部署の社員だったのを専属にしちゃったんです。
岸本 プロセスの中で、ポテンシャルを持っている将来のキーパーソン候補を見つけてそっちのほうへうまく育てていくということですね。
小堀 そうそう。KDKHの「H」は「人」ですが、人が育つということがワークショップの魅力ですよね。非常にうまくいくケースはなかなかいないんですよ。
岸本 たとえ面白いものができても、それを使いこなせる人がいないといけないですよね。
小堀 経営者はすべてを理解しようとしますが、じつは想像を超えた部分にこそイノベーションやチャンスがあるんです。僕自身、今までの経験上でデザインをまとめようとしてしまうことがある。所員にデザインさせて、まったく想像しなかったようなものが出てきたとき、「これダメだよ」と言うのか、「これすげぇな」と言えるリテラシーを持てるかが大事なんです。自分の可能性を自分で開けられるリテラシーがないと面白くないと思うんですよね。ある意味リスクですが、ひとつのクリエーションの源泉でもある。
岸本 「やってみなはれ」というのは簡単ではありませんね。
小堀 保守的にいくのか、リベラルにいくのか。最近、「アリさんとキリギリス」という本を紹介してもらいました。アリは保守的で働き者、キリギリスは怠け者だがイノベーターで永遠に噛み合わないから、その中間の人が要るという話らしい。企業にはそういう人がいるんだろうという気がします。
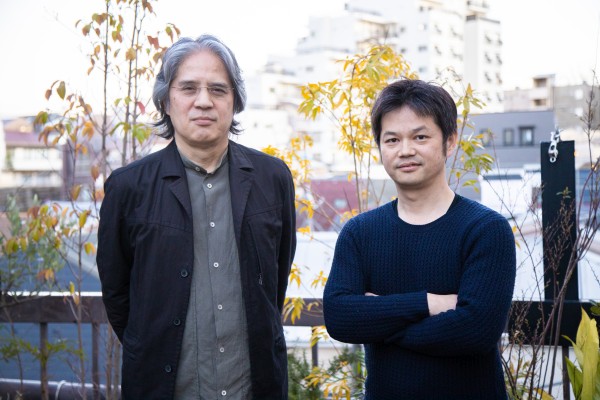
(左) 岸本章弘氏(ワークスケープラボ)、(右) 小堀哲夫氏 (小堀哲夫建築事務所)
■インタビューを終えて(岸本章弘)
前半では、形を使ってユーザーの気付きを促し、思考の枠を広げ、柔軟な発想を触発するプロセスの様子を話していただいた。多くの読者にとって刺激となる内容だったと思う。オフィスづくりにかかわるプランナーのひとりとしても、自身のプロセスや手法のアップデートを考えるためのヒントが見つかった気がしている。
後半の話題の中心は、これからのワークプレイス。働き方やマネジメントの動向について、自身やチームの経験や試行とも重ね合わせながら語る様子が印象に残った。そうした思考の姿勢が、抽象的な理念や理論に加えて、身体感覚ともいえそうな現実味ある価値軸を与えているのかもしれない。
トライ&ラーンの繰り返しという小堀氏が、次のプロジェクトでは誰をチームに巻き込み、どんな新たなトライを見せてくれるか、ますます楽しみになった。
(岸本章弘)
プロフィール
小堀哲夫(こぼり てつお)
建築家・小堀哲夫建築設計事務所 代表
1971年岐阜県生まれ。法政大学大学院工学研究科建設工学専攻修士課程修了。大手設計会社を経て、2008年に小堀哲夫建築設計事務所設立。法政大学 デザイン工学部建築学科教授、梅光学院大学客員教授、名古屋工業大学非常勤講師を務める。2017年には「JIA日本建築大賞」と「日本建築学会賞」の二大建築賞を史上初となる同年内でダブル受賞し注目を集めたほか、2019年には福井県内で手がけた日華化学・NICCA INNOVATION CENTERが自身2度目となるJIA日本建築大賞を受賞。
岸本 章弘(きしもと あきひろ)
ワークスケープ・ラボ代表
オフィス家具メーカーにてオフィス等の設計と研究開発、次世代ワークプレイスのコンセプト開発とプロトタイプデザインに携わり、オフィス研究情報誌 『ECIFFO』 編集長をつとめる。2007年に独立し、ワークプレイスのデザインと研究の分野でコンサルティング活動をおこなっている。
千葉工業大学、京都工芸繊維大学大学院にて非常勤講師等を歴任。
著書『NEW WORKSCAPE 仕事を変えるオフィスのデザイン』(2011)、『POST-OFFICE ワークスペース改造計画』(共著、2006)
ワークスケープ・ラボ [外部リンク]
取材協力
小堀哲夫建築事務所[外部リンク]
編集・文・撮影:アスクル「みんなの仕事場」運営事務局 (※印の画像を除く)
取材日:2019年2月27日
2016年11月17日のリニューアル前の旧コンテンツは
こちらからご確認ください。